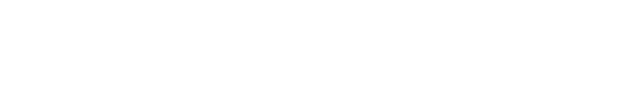高血圧とは
血圧とは、心臓が血液を押し出すときに血管の壁にかかる圧力のことです。
血圧は通常は120/70mmHgといったように、「上の血圧/下の血圧」という順番で表記されます。上の血圧は「収縮期血圧」と呼ばれ、心臓が収縮して血液が送り出された時の血圧を、下の血圧は「拡張期血圧」と呼ばれ、心臓が緩んで血液が戻って来る時の血圧を指します。この2つのうち、どちらかが基準を上回った時に高血圧と呼ばれます。
血圧は心臓がより強く収縮するほど、また血管がより硬いほど上昇します。この血圧が一定ラインを超えたときに、高血圧と呼ばれます。
心臓が強く収縮する状態として、例えば走ったり重いものを持ったりといった動作による一時的な影響、ストレスや睡眠不足による自律神経の緊張、甲状腺や副腎といったホルモンの病気などが挙げられます。
血管が硬くなる要因としては、糖尿病や脂質異常症、喫煙といった生活習慣による慢性的な影響があります。
血圧の基準値
日本高血圧学会が発行する高血圧治療ガイドラインでは、高血圧の定義は以下の表のように定義されております。
| 分類 | 診察室血圧(mmHg) | 家庭血圧(mmHg) | ||
| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |
| 正常血圧 | <120 かつ <80 | <115 かつ <75 | ||
| 正常高値血圧 | 120-129 かつ <80 | 125-124 かつ <75 | ||
| 高値血圧 | 130-139 かつ/または 80-89 | 125-134 かつ/または 75-84 | ||
| 高血圧 | ≧140 かつ/または ≧90 | ≧135 かつ/または ≧85 | ||
(日本高血圧学会:高血圧治療ガイドライン2019)
ひとつの基準として、病院の診察室で測定した血圧が140/90mmHgを超えた場合には高血圧と呼ばれます。
_
血圧が高いと何が困るのか
高血圧になると何が困るのでしょうか?
実は、血圧が高いからと言って、何かすぐに症状が出るわけではありません。高血圧はサイレント・キラーなどと呼ばれ、本人の気づかないうちに動脈硬化が進行し、やがて重大な血管系の病気を引き起こすリスクに繋がります。
高血圧の本質的な問題は「動脈硬化」にあります。
血圧が高いと、血管の内側の壁が傷つきやすくなります。この傷ついた壁を治そうとする仕組みが体には備わっているのですが、治す過程でいろいろな物質が血管の壁にこびりつきます。すると、元の血管よりも壁が厚くなった状態で修復されるのです。
このような血管は、元の正常な血管よりも壁が厚くなった分だけ弾力性に欠け、壁が固くなります。
先の項で説明したとおり、血圧は血管の壁が硬いほど高くなりますので、高血圧によって壁が傷つき動脈が固くなると、さらに血圧が上がるという負のサイクルに入ります。
また、血管の壁の傷を治す過程で余計な物質がこびりついた分だけ、血管の内側の血液が通るスペースが狭くなります。これを繰り返していくと、細い血管が詰まったり血流が悪くなる原因となります。
これが心臓の周りの血管に起これば狭心症や心筋梗塞となり、脳の血管に起これば脳梗塞となります。いずれも命に関わったり後遺症を残す可能性のある重大な病気です。
高血圧になると、このように動脈硬化が進行し、それによって更に血圧が上がるとともに、危ない病気になるリスクが上がるのです。
_
血圧が上がる原因
高血圧には2つの種類があり、それぞれで原因が異なります。
- 本態性高血圧 体質や生活習慣が原因で起こる高血圧
- 二次性高血圧 ホルモンの異常など他の病気が原因で起こる高血圧
本態性高血圧は、遺伝的な体質で高血圧になりやすいベースがある場合に、塩分のとりすぎ、運動不足、喫煙、過度な飲酒、ストレス、加齢などの生活習慣が重なって起こります。血圧を下げるために生活習慣を見直していくことが必要です。高血圧の多くはこの本態性高血圧です。
二次性高血圧は、他の病気が原因で起こります。例えば首のあたりには甲状腺という代謝をコントロールする臓器があります。この甲状腺からホルモンが出すぎてしまう病気は甲状腺機能亢進症と呼ばれますが、この過剰に分泌された甲状腺ホルモンによって血圧が上がります。この場合、治療はホルモンの量を抑えることになります。このように他の病気が原因で起こる二次性高血圧の場合には、原因となっている病気の治療をすることが、血圧の治療に繋がります。
自身が高血圧になったときに、それはどちらのタイプの高血圧かを判断するためにはいくつかの検査が必要ですが、詳しい検査に踏み切るための基準があります。
①発症が早い(20-30代などの若い時から高血圧)
②急速に悪化している
③薬が効かない
④血液検査でミネラルのバランスが崩れている
他にもいくつかありますが、代表的にはこのような項目に当てはまったときに
二次性高血圧かどうかの詳しい検査をおすすめしています。
_
高血圧の治療
ここでは本態性高血圧の治療についてお話します。
(二次性高血圧の治療は、原因になっている病気の治療になりますので、また別のお話です)
高血圧(本態性高血圧)の治療は主に
1.食事に気をつけ、運動習慣を改善する
2.血圧を下げる薬を飲む
この2つがメインです。
血圧を下げる薬(降圧剤)に関しては、いくつかの種類があり、患者さんの状態に応じて医師が選ぶことになります。飲めば一定の効果はありますが、なるべくなら薬を飲まずに治したいですよね。その場合、見直すべき生活習慣は下記の6項目です。
- 塩分を取りすぎない
- 適度な運動をする
- 肥満を改善する
- ストレスを貯めない
- カリウムを十分とる
- 酒・タバコを控える
ご自身の生活に思い当たる節がある場合、まずはこれらを見直してみては如何でしょうか?
さらに詳しい内容を医師とご相談されたい方、高血圧の治療でお悩みの方は
ぜひ一度、葛飾区金町の中沢内科胃腸科医院までご相談下さい!